Share
合鍵で彼の部屋へ、誕生日サプライズのはずが…洗面台の『見知らぬ歯ブラシ』が告げた絶望【短編小説】
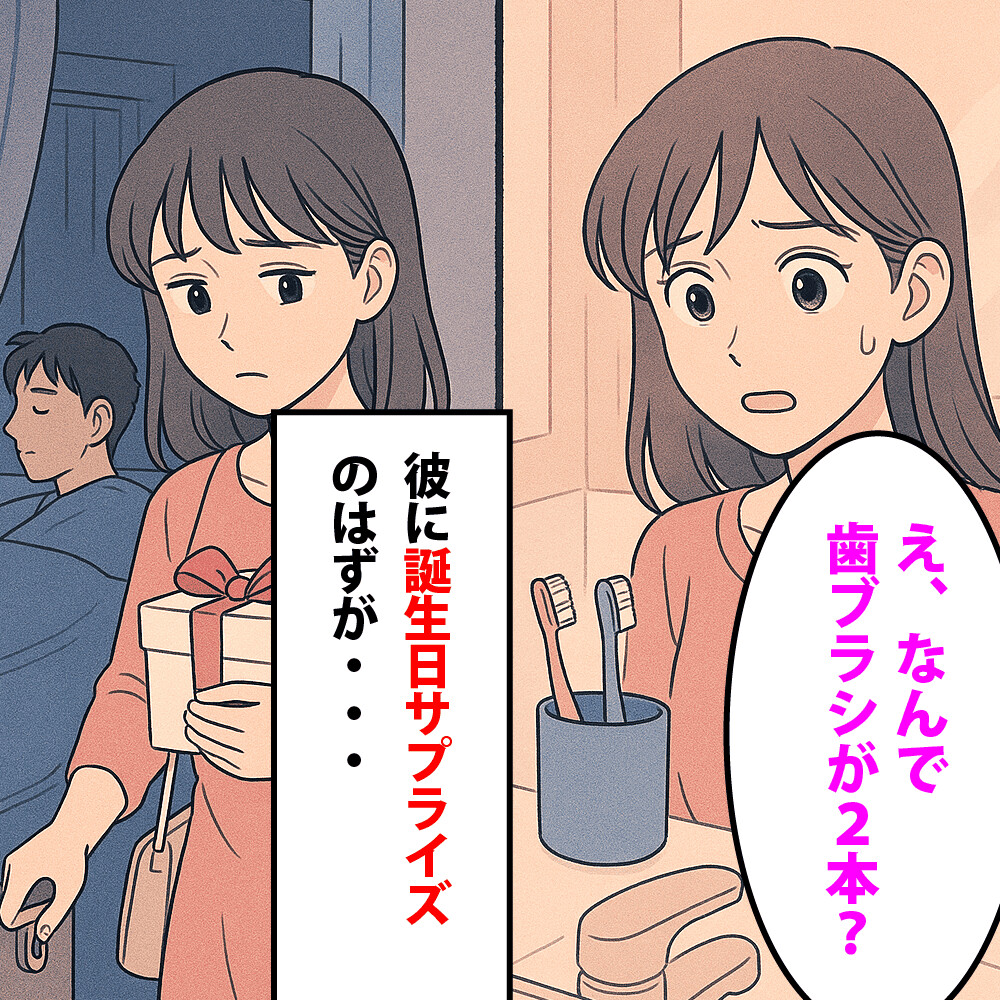
サプライズのはずが
彼の誕生日の朝、私は合鍵を握りしめ、そっと彼の部屋のドアを開けました。
早起きして買ったケーキとプレゼントを手に、キッチンでコーヒーを淹れて、驚かせようと思っていたのです。
部屋は静まり返り、カーテンの隙間から差し込む光が、ゆっくりと床を照らしていました。
彼はまだ眠っているのだろうと思い、私は足音を忍ばせて洗面所へ向かいました。手を洗い、少し身だしなみを整えてから、朝食を用意しようと考えていました。
予想外の光景
蛇口をひねった瞬間、ふと視線が横に向きました。そこには、コップに立てかけられた二本の歯ブラシ。
片方は見慣れた彼のもの、もう片方は、私が使っているものとは明らかに違う女性用の歯ブラシでした。
色もデザインも、女性らしい柔らかい色合い。新品ではなく、確かに何度も使われている形跡がありました。
その存在が、この部屋で何が起きていたのかを雄弁に物語っていました。私は一歩後ずさりし、胸の奥に冷たいものが広がっていくのを感じました。
動揺と確信
心臓が早鐘を打ち、手に持っていたマグカップがわずかに震えました。
「誰の?」と口に出すことはしませんでした。答えはもう分かっていたからです。
それでも、何事もなかったかのようにコーヒーを淹れ、ケーキの箱を開けました。
ドアの向こうから、彼が眠たそうな顔で現れます。その笑顔を見た瞬間、私の中で何かが静かに切れました。
彼の誕生日を祝うために来たはずなのに、もうその気持ちはどこにもありませんでした。
置いてきたもの
誕生日の歌もプレゼントも、結局渡さずに帰りました。
代わりに、洗面台の前に小さなメモを置きました。「二本目の歯ブラシ、お似合いだね」とだけ書いて。
ドアを閉めたとき、外の空気が妙に冷たく感じました。
あの二本の歯ブラシは、私の知らない時間と裏切りの証でした。
そして同時に、この恋の終わりを告げる最後の合図でもあったのです。帰り道、手に残ったケーキの箱がやけに重く感じられ、足取りは自然と早くなっていました。
本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。
Feature
特集記事















































