Share
「君のためを思って言うんだけどね」モラハラ彼氏の洗脳。目を覚ましたのは、親友の一言だった【短編小説】
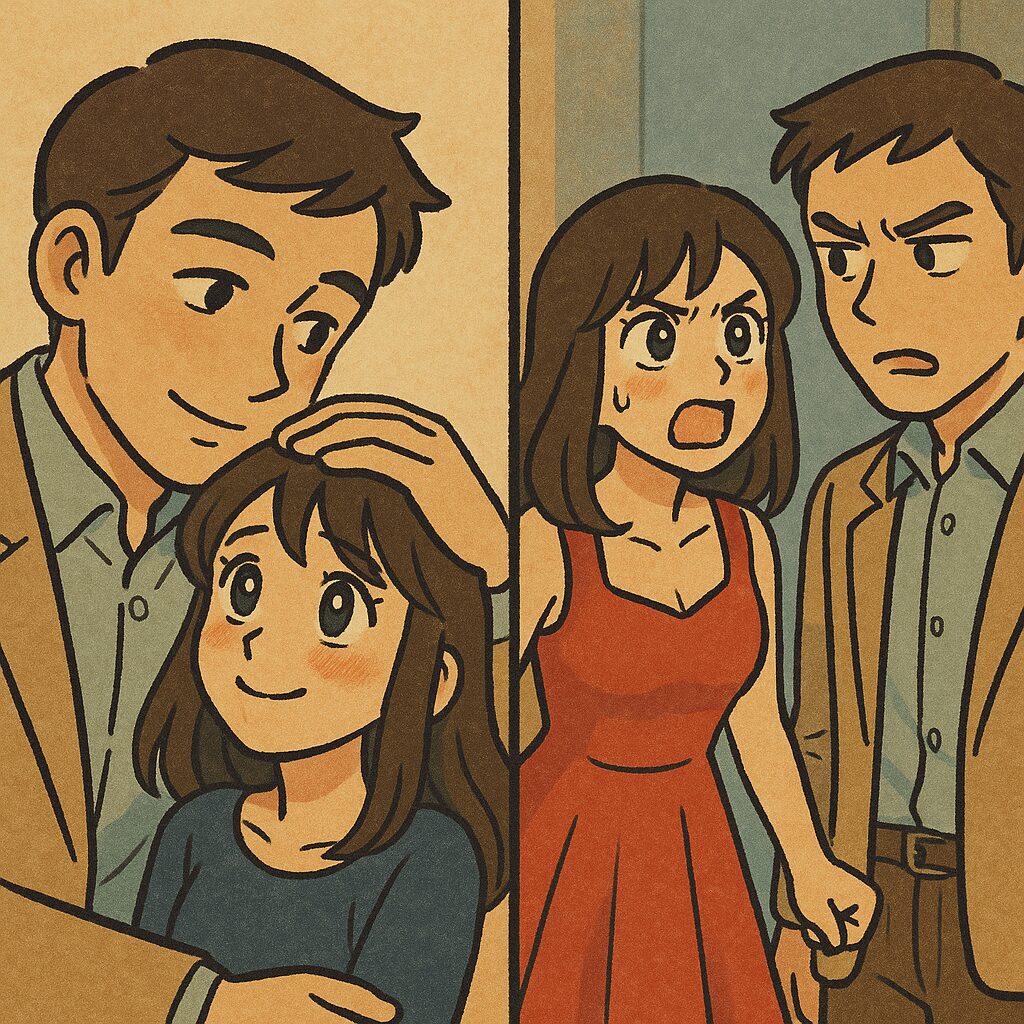
気づかぬうちに蝕まれていく心
大輝さんと付き合い始めた当初、私は世界で一番幸せだと思っていました。
彼はいつも穏やかで、私のことを「誰よりも大切だ」と言ってくれました。
「彩香のためを思って言うんだけどね」と前置きされるアドバイスは、いつも的確なように思えたのです。
「その服、君には少し派手じゃないかな?こっちの方が上品に見えるよ」
「友達との付き合いも大事だけど、僕との時間をもっと大切にしてほしいな。君がいないと寂しいんだ」
彼の言葉は、すべて私を思ってのこと。そう信じていました。
彼の言う通りにすれば、彼は満足そうに微笑み、「やっぱり君は素直で良い子だね」と頭を撫でてくれるのです。
いつしか私は、自分の意思で何かを決めることが怖くなっていました。
大輝の望む「私」でいることが、愛情を得る唯一の方法だと、心のどこかで思い込んでしまっていたのです。
彼が少しでも不機嫌になると、「私が何か悪いことをしたんだ」と、すべて私のせいだと感じ、胸が締め付けられるような思いでした。
友人の一言で覚めた悪夢
そんなある日、久しぶりに会った友人の詩織の一言が、私の目を覚まさせました。
「それって本当に彩香のため?大輝さんの言いなりになってるだけじゃない?」
その言葉に、頭を殴られたような衝撃を受けました。そうだ、私は私の人生を生きていなかった。
その日の夜、私はクローゼットの奥から、彼に「派手だ」と言われて封印していたお気に入りの赤いワンピースを取り出して着ました。
帰宅した大輝は、私を見るなり眉をひそめます。
「どうしたんだいその服。君のためを思って言ったのに…」
「もうやめて」私は彼の言葉を遮り、冷静に、でもはっきりと告げました。
「あなたの『ため』は、いつも大輝のためだったじゃない。私が私の好きな服を着て、好きな友達に会うのが、そんなに嫌だった?思い通りにならないと、不機嫌になるのよね」
彼の優しい仮面が剥がれ落ち、顔が怒りで歪みました。
「なんだその言い方は!俺がどれだけお前のことを…」
「もう結構よ」私は彼の言葉を再び遮り、玄関に向かいました。「あなたの作った籠の中は、もう息苦しいの。さようなら」
呆然と立ち尽くす彼を背にドアを開けた瞬間、冷たい夜の空気が信じられないほど美味しく感じました。
やっと、本当の私になれる。そう思うと、自然と笑みがこぼれていました。
本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。
※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。
※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。
友だち登録&アンケート回答で「Amazonギフトカード」など好きな商品を選べるギフトを毎月抽選で5名様にプレゼント!
\ 今すぐ応募する /
Feature
特集記事















































