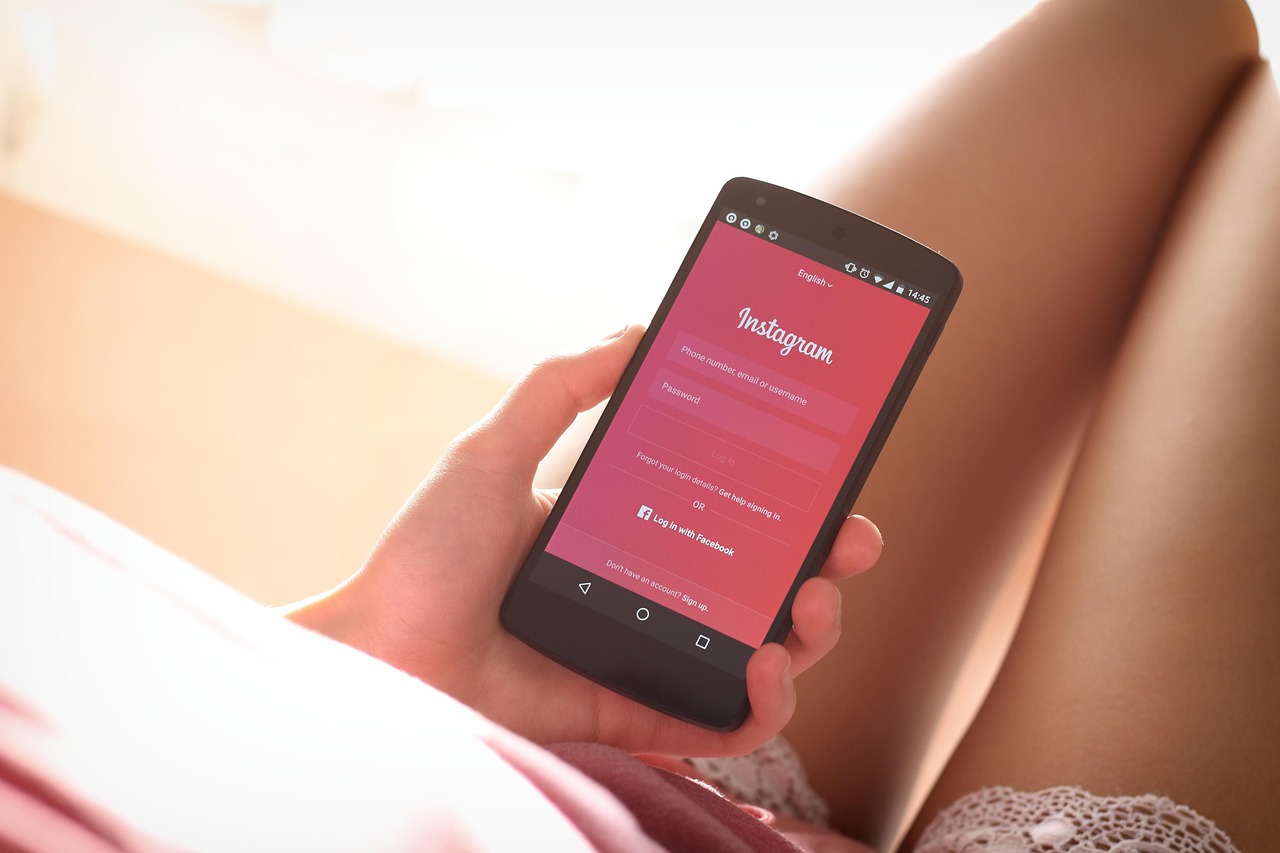Share
4年間母の介護を私に押し付けた妹。葬式で『感動的な弔辞』を読み始めた彼女に私が下した決断【短編小説】

「お姉ちゃん、お母さんのことお願いね」
母が倒れてからの4年間、私はこの言葉を何百回聞いたかわからない。遠方に住み、結婚して子どももいる妹が、顔を見せに来たのはたったの数回。そのたびに、お土産のデパートのお菓子を置いて、嵐のように去っていく。介護保険の手続きも、毎日の食事の介助も、夜中の見守りも、全てが私の役目だった。
友人の結婚式に出ることも、旅行に行くことも諦めた。自分の人生は止まったままなのに、妹はSNSで子どもの運動会や家族旅行の写真を投稿していた。悔しいとか、悲しいとか、もうそんな感情すら湧かなかった。ただただ、この介護が終わる日を夢見ていた。
私の人生を捧げた、母との日々
母は次第に会話もままならなくなり、私との時間もほとんど眠って過ごすようになった。それでも、握りしめた母の手の温かさだけが、私をこの場所に繋ぎとめていた。妹からの連絡は、「お母さんどう?」の一言だけ。私が「大変だから少し手伝ってくれない?」と漏らすと、「でも、お姉ちゃんの方がお母さんのことよく知ってるから…」と、決まって話をはぐらかされた。
母は、私の人生の全てだった。私の青春も、キャリアも、そして自由も、母の介護に捧げてきた。誰に褒められることもなく、感謝されることもなく、ただ毎日を必死に生きてきた。そんな日々が、つい先日、母の安らかな眠りによって終わりを告げた。
妹の“感動的な”弔辞、そして私の決断
母の葬儀の日。遺影の前で、私は静かに座っていた。母を亡くした悲しみと、ようやく訪れた解放感とが入り混じった、複雑な気持ちだった。そんな中、弔辞を読むために前に出たのは、妹だった。
マイクを握った妹は、涙をこぼしながら語り始めた。「お母さん、ありがとう。大変な中、いつも笑顔でいてくれて…」。まるで、毎日寄り添っていたかのような、感動的な弔辞。彼女が語るエピソードのほとんどは、遠い昔の話か、誇張されたものばかりだった。
その瞬間、私の心の中で何かがプツンと切れた。私は、静かに立ち上がり、会場のドアに向かって歩き出した。妹の「お姉ちゃん?」という声が聞こえた気がしたが、振り返らなかった。
母を一人にすることはなかった。ただ、もう誰かのために、自分を犠牲にすることはしない。私は、私の人生を生きることを決めたのだ。
本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

GLAM Entame Editorial
編集部
エンタメやカルチャーを入り口に、今を生きる大人の感性や知的好奇心を刺激する編集部チームです。話題のニュースやトレンド、SNSで広がるカルチャーから、思わず考えたくなる大人の常識クイズまで。楽しみながら学び、視野を広げられるコンテンツを通して、日常にちょっとした発見や会話のきっかけを届けています。ただ消費するだけのエンタメではなく、知ること・考えること・共有することを大切に。大人だからこそ楽しめるポップカルチャーを、発信しています。
Feature
特集記事