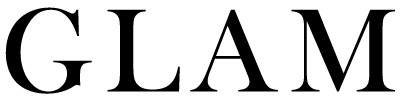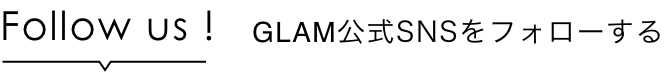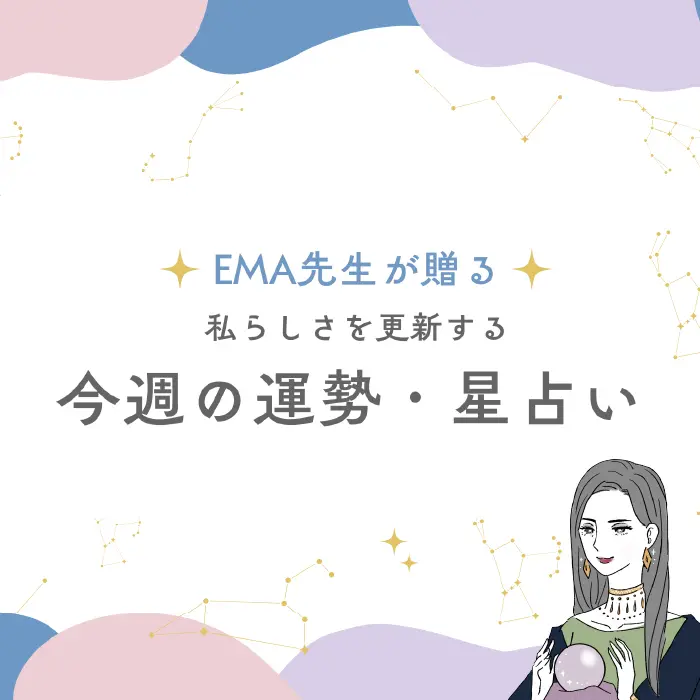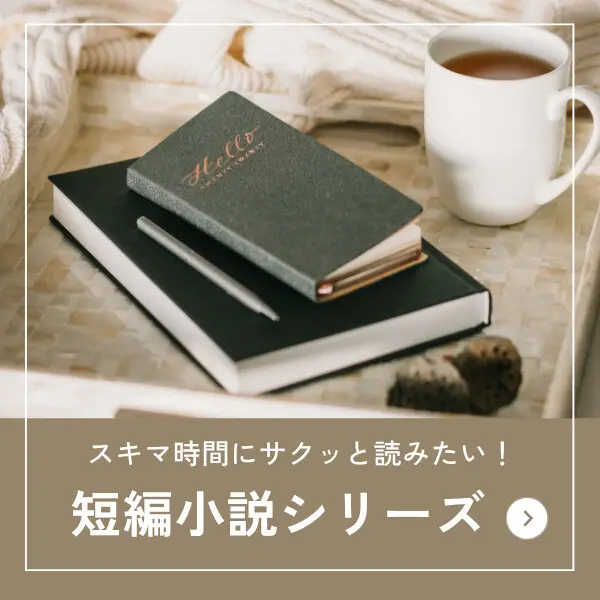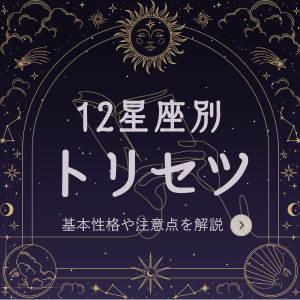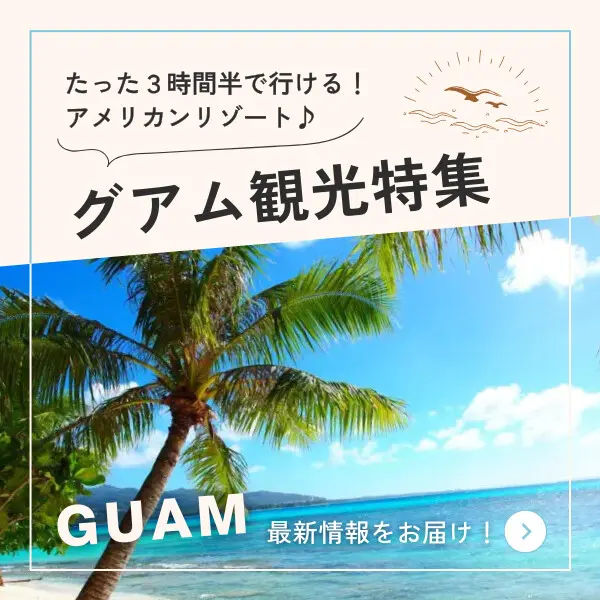Share
悲劇のヒロイン症候群とは?原因と末路、卒業するための克服法を徹底解説
INDEX
そもそも「悲劇のヒロイン症候群」とは?

チェックリストで、自分でも気づかなかった心のクセが見えてきたかもしれませんね。では、改めて「悲劇のヒロイン症候群」とは一体どういうものなのでしょうか。
これは、先ほども触れたように医学的な病名や正式な精神疾患ではありません。心理学の用語でもなく、主に日常会話で使われる言葉です。簡単に言うと、「自分は誰よりも不幸だ」と思い込み、その不幸な自分に浸ることで、無意識に心の安定を得ようとする状態や、そうした傾向にある人のことを指します。
物語のヒロインが困難を乗り越えて愛されるように、「不幸で可哀想な私」でいることで、周りからの同情や関心を引き、自分の存在価値を確認しようとするのです。
SNS、恋愛、職場…場面別「あるある」な言動
悲劇のヒロイン症候群の傾向は、私たちの日常の様々な場面に顔を出します。あなたにも、思わず「あるある!」と頷いてしまうものがあるかもしれません。
SNSでの「あるある」
「また熱出た…誰も心配してくれないけど」「深夜に一人で涙が止まらない…」といった、誰にともなく発信する“かまってちゃん”な投稿が特徴です。「大丈夫?」というコメントやDMがつくことで、「私は気にかけてもらえている」と安心感を得ます。幸せな投稿には「いいね」を押さず、他人の不幸話には敏感に反応する、なんてことも。
恋愛での「あるある」
「どうせ私のことなんて、本当は好きじゃないんでしょ?」と恋人を試したり、わざと連絡を無視して心配させたり。順調な関係が続くと、無意識に問題を起こして「愛されているか」を確認しようとします。彼からの愛情を素直に受け取れず、「こんなに尽くしているのに、彼は分かってくれない」と、常に自分が被害者であるかのようなストーリーを作り上げてしまいがちです。
職場での「あるある」
「この仕事、全部私がやってるんです」「誰も手伝ってくれなくて…」と、常に自分が一番大変であるかのように振る舞います。周りからの「頑張ってるね」「無理しないでね」という言葉が、何よりの栄養源。ミスをした時には、「最近、色々あって…」と不幸な境遇を言い訳にし、自分を守ろうとする傾向もあります。
なぜなってしまうの?悲劇のヒロイン症候群の3つの心理的背景
では、どうして私たちは「悲劇のヒロイン」になってしまうのでしょうか。その背景には、自分でも気づいていない、複雑な心が隠されています。
決して、あなたが意地悪でそうしているわけではないのです。その心の奥を、そっと覗いてみましょう。
①「不幸な私」でいたい。低い自己肯定感と承認欲求
心の深いところに、「ありのままの自分には価値がない」という思い込みが隠れていませんか?
自分に自信が持てないとき、「可哀想な私」でいることは、実はとても簡単な自己アピールの手段になります。
「大変だね」「頑張ってるね」という同情や励ましの言葉は、「私は注目される価値のある人間だ」という承認欲求を一時的に満たしてくれる、甘い蜜のようなもの。
幸せになることよりも、「不幸」という名のスポットライトを浴び続けることを、無意識に選んでしまっているのです。
②周りをコントロールしたい。無意識の独占欲と依存心
「私がこんなに辛いんだから、あなたも心配して当然でしょ?」
口には出さなくても、そんな風に周りの人の感情をコントロールしようとする気持ちが働いていることがあります。
自分の不幸をアピールすることで、恋人や友人の関心を自分だけに向けさせ、離れていかないように縛り付けようとするのです。
これは、相手を信頼できず、自分一人では立っていられないという、強い依存心の裏返しでもあります。「可哀想な私」を見捨てる人はいないだろう、という計算が、無意識のうちに働いてしまっているのかもしれません。
③過去のトラウマや家庭環境の影響
今の思考のクセは、もしかしたら、ずっと昔の経験が原因になっているのかもしれません。
例えば、子供の頃、病気や怪我をした時だけ親が優しくしてくれた、という経験はありませんか?あるいは、兄弟と比べられ、常に「良い子」でいなければ認めてもらえなかった、など。
そんな経験が、「普通の状態では愛されない」「何か問題があった方が気にかけてもらえる」という、心の傷や歪んだ学習となって、大人になった今も、あなたの行動に影響を与えている可能性があるのです。
Feature
おすすめ記事