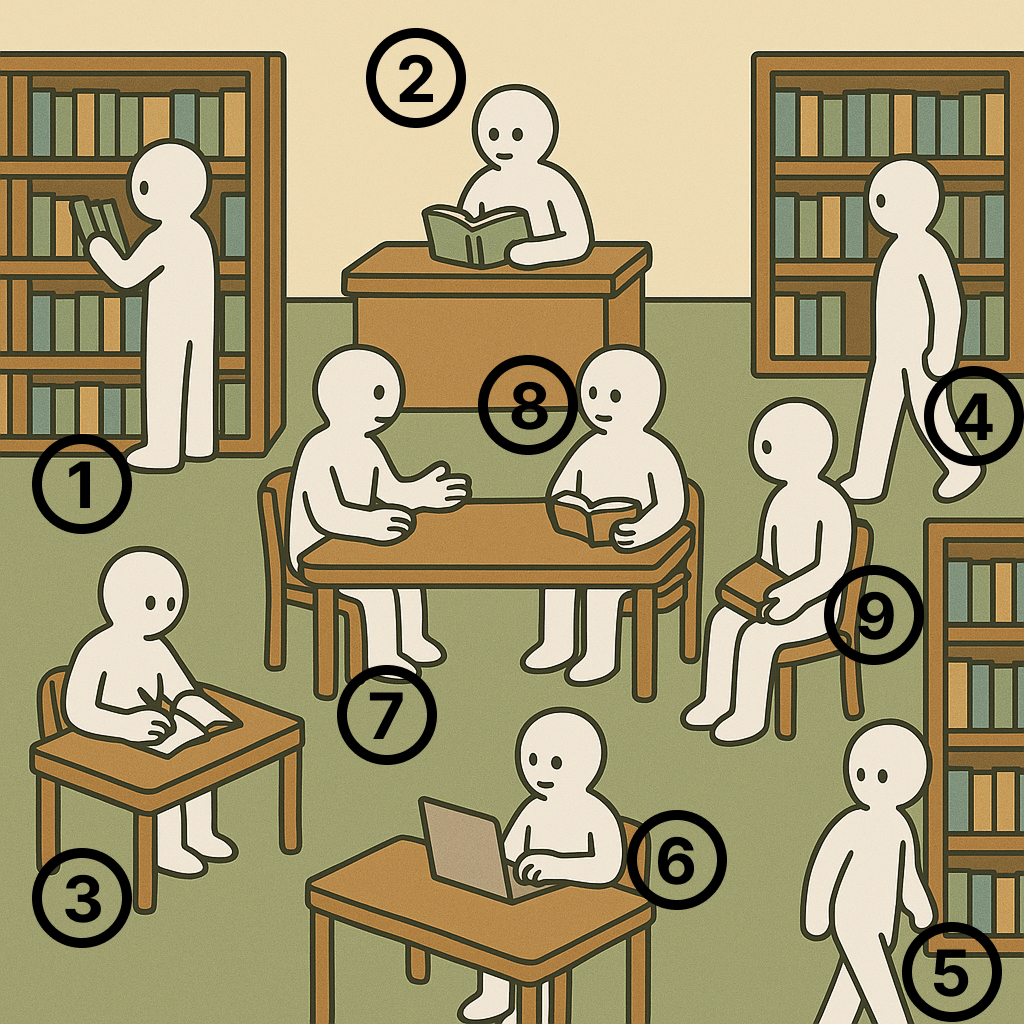Share
部屋にあった“知らない香水”。彼の“沈黙”が、何より雄弁な“答え”だった。彼を捨てた日【短編小説】

謎の香水の香りに違和感を持った
付き合って1年になる彼氏、翔太の部屋で過ごす時間は、私にとって安らぎそのものでした。
その日も、彼が淹れてくれたコーヒーを飲みながら、くつろいだ時間を過ごしていました。
ふと、部屋に漂う甘い香りに気がつきました。
私の使う香水ではないし、彼の柔軟剤の香りとも違う、華やかで女性らしい香りです。
「あれ?」
香りの元を探して部屋を見渡すと、本棚の隅に、見慣れない小さなガラス瓶が置かれているのが目に入りました。
ピンクゴールドのキャップがついた、可愛らしいデザインの香水瓶。
それは、私が絶対に選ばないような、甘く可憐なデザインでした。
ちょうどシャワーから上がってきた翔太に、努めて平静を装って尋ねます。
「ねぇ、この香り、誰の?」
私の手にある香水瓶を見た瞬間、翔太の動きがぴたりと止まりました。
彼の目は、私の顔と香水瓶とを慌ただしく行き来しています。
「さあ?知らないけど」
あまりにも早い、そして投げやりな返事でした。
追求を続ける私に彼が言ったのは…
「知らないって、どういうこと?知らない人の香水が、どうして翔太の部屋にあるの?」
「いや、だから知らないって。友達が来た時にでも忘れていったんじゃないの?」
「最近、うちに友達呼んだなんて言ってなかったじゃない」
私が問い詰めると、彼はどんどん不機嫌になり、最後には「しつこいな!知らないって言ってるだろ!」と声を荒げました。
その必死な様子が、何よりも雄弁に答えを物語っていました。
本当にやましいことがなければ、こんなに頑なになる必要はないはずです。
一緒に持ち主を考えてくれたり、「今度友達に聞いてみるよ」と言ってくれたりしてもいいはず。
彼が選んだのは、私を「しつこい」と突き放し、香水の持ち主をかばうことでした。
その甘い香りが、急に鼻をつく不快な匂いに変わったように感じました。
私は黙って、香水瓶を元の場所に戻しました。
重い沈黙が部屋に流れます。彼は気まずそうに私を見ていましたが、それ以上何も言いませんでした。
きっと、これからも彼は「知らない」と言い続けるのでしょう。
「そっか、知らないんだね」
その一言だけを残して、私は静かに荷物をまとめ、彼の部屋を出ました。
翔太は私を止めませんでした。
結局、彼は最後まで、あの香水の持ち主が誰なのかを答えることはありませんでした。
でも、もうその必要はなかったのです。彼の沈黙が、私知りたくなかった全ての答えでしたから。
本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。
Feature
特集記事